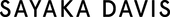INTERVIEW
写真家 壹岐倫子さん (後半)
Text & Edit:Eriko Azuma
ものづくりは、あらゆるものに宿る命の温度を繋いでいくこと。
時代を超えて育まれた美しいクラフトマンシップに焦点をあて、心動かされる「ものづくり」の背景を紐解いていきます。
写真とダンス、アプローチの異なる2つの表現を、多重露光による幻想的な作品として発表しているアーティストの壹岐倫子さん。ダンサーでもある壹岐さんが自然の中で踊り、光と重ねることで、見えてくるものは何か、自然と人間とは何かを問いかける作品「DANCE」を、女性の美しさを引き出すSAYAAKA DAVIS のパターンにのせた美しいカプセルコレクションが、ブランド設立10周年を記念して誕生しました。対談後編では、壹岐さんの創作活動の根幹である「ダンスと写真」についてより深く話を伺いました。
表現したいものをビジュアル化したい。そのツールとして写真を選択
Sayaka Tokitomo Davis(以下Sayaka): 壹岐さんがどのような子供時代を経て現在の作品を作るようになったのか興味があります。子供の頃、どんなことに夢中になっていましたか?
壹岐倫子(以下壹岐):幼い頃は植物が好きで、近くに住む祖母と一緒によく庭いじりをしていました。植物の名前を教えてもらったり、姫林檎の木に実がなるのをワクワク楽しみにしたり、そんな祖母との時間が印象に残っています。春になると水仙や薔薇が咲き、四季折々の花が楽しめる祖母の庭で、季節の移り変わりや自然の営みを体験させてもらったのは大きかったと思います。
Sayaka:壹岐さんとお話していると、作品も子育ても自然とのつながりをすごく大事にしているなと思うのですが、そんな幼少時代の体験が今に繋がっているのかもしれませんね。写真にも小さい頃から興味があったんですか?
壹岐:最初に興味を抱いたのは高校生の頃。私は絵が好きで、小学校から高校まで油絵をやっていたんです。何かビジュアル的なものを作りたいという思いを抱いていたのですが、油絵は絵の具を重ねて、乾くのを待ってまた重ねてと、表現したいことをすぐ形にできるわけじゃない。表現したいことをすぐにビジュアル化したい、たくさん形にしたいという気持ちがあって、だったら写真はどうだろう?と思いました。母方の祖父が趣味で写真をやっていたのでカメラが身近な存在だったというのもあるかもしれません。当時、HOLGAというトイカメラが流行していて、それを買って何の知識も技術もないままに撮り始めました。美大や写真の大学に進みたい気持ちはあったのですが、両親に反対されたこともあり、インテリアデザインの大学に進学しました。

Sayaka:大学時代、壹岐さんにとって写真はどういう存在でしたか?
壹岐:進学したのは女子大だったのですが、当時の建築業界は男性中心で、どんなに優秀でも建築事務所に就職できる人はほんのわずか。就職活動を前に改めてやりたいことを考えた時、やっぱり写真という存在が引っかかって。成人のお祝いでデジタル一眼レフを買ってもらったり、写真屋さんでバイトを始めたりして本格的に写真を勉強したいと思った時、フリーランスのカメラマンさんを紹介してもらいました。初めて仕事としての写真を知り、すごくかっこいいと衝撃を受けたんです。アシスタントして様々な現場でライティングなどを教えてもらいつつ、写真館でもバイトをしたり、S NSを通じて興味のあるカメラマンさんにコンタクトを取って話を聞いたりと、貪欲に学びました。技術を身につけたら自分が表現したかったことが叶えられて、どんどん写真が楽しくなってきて。大学を卒業する頃には少しずつ仕事がもらえるようになっていました。就職せずにフリーのカメラマンになることは両親に反対されたのですが、「1年だけやらせてほしい」とお願いして今に至ります。最初はブライダルの仕事で経済的な基盤を作りながら、色々な撮影を経験しました。
Sayaka:大学時代から本格的に写真を初めて、卒業する頃には仕事に繋がっているなんてすごいですね。コマーシャルフォトとアートフォトって同じ写真でも違うジャンルだと思うのですが、自分の表現方法として写真を使いたいと思うようになったのはいつ頃でしょうか?
壹岐:最初はとにかく技術を身につけてお客様が求める写真を撮りたい、カメラマンとして食べていきたい。という気持ちが強かったんですが、求められる写真を撮り続けていると、私の写真って何だろう。と思うようになってきて。大学時代の自分は何がやりたかったんだろうって立ち止まって考えた時に「写真とダンス」が出てきたんです。
自分自身を踊る... 突き動かされるように没入したダンスの世界
Sayaka:ダンスはどんなきっかけで始めたんですか?
壹岐:ダンスは振り付けを踊るイメージがあったのであまり好きじゃないと思っていたのですが、ちょうど写真を始めたのと同じ頃、映画に影響を受けてベリーダンスを習い始めました。そこで出会った友人が「振り付けに囚われず、自分を踊ればいいんだよ」と教えてくれてたんです。そんな風に踊ってみると、ダンスはご飯を食べるのと同じように、人間が本来持っている本能的な欲求だと気が付き、何かに突き動かされるような気持ちで踊りたいと思うようになりました。同じ感覚を持つ仲間で集まって踊ったり、自分の感覚に合うダンサーのワークショップに参加したりしながら自分のスタイルを見つけていきました。
舞台やショーに出ることもありましたが、写真と違って職業にしたいわけではなかったので、感覚的に没入できたんだと思います。お金をもらって舞台で踊る人をダンサーと呼ぶのなら、私はダンサーではないかもしれません。でも人は皆ダンサーだと思っていて、どの人も踊れるし踊りたいという気持ちを基本的な欲求として持っているはず。踊ることで解放されたり、今まで気づかなかった感覚と繋がったり、より深く自分と繋がったりとか、そういう体験を通して自分が表現したいスタイルに近づいてきた感覚です。体を動かしながらの気づきはダイレクトで強い。瞑想に近いのかなって思ったりします。
Sayaka:私も興味があってダンスを習ってみたことがあるんですが、恥ずかしい気持ちがあったり型に囚われてしまったりして、自分を解放するという体験は叶わなかったですね。
壹岐:ダンスはリードしてくれる先生の力量で変わってくるし、何度も経験することで、自分と音楽がコネクトできるようになる。いい先生はその人自身を引き出してくれるんです。鍛錬を重ねた技術の先に、完全に自分と一致したダンスを踊れる人って本当に素晴らしいけれど、なかなかいない。ダンスも写真も、技術を身につけることで表現が狭まってしまうところがあるんです。知識があることできないと思い込んでしまうことを、いかに柔軟に飛び越えていけるか。鍛錬の先で自分を表現することは、誰もができることではないかもしれませんが、私は自分と繋がるツールとして、ダンスも写真も続けていきたいと思っています。

Sayaka:自分と繋がるってどんな感覚なんでしょう。
壱岐:トランス状態に近い感覚でしょうか。盆踊りとかずっとひたすら同じ踊りをするのは、昔の人たちが見えない恐れとか祈り、見えない何かと繋がるための一つの手段だったのかなと思っています。感じることは人それぞれだと思いますが、私の場合は日々悶々と考えていたことが、やっぱりこうだったんだと腑に落ちる瞬間があったり、地球の一部だと感じられる瞬間があったりして、それが喜びです。
Sayaka:フィジカルに同じ動きを繰り返して現実から自分を引き離して瞑想のような状態に持っていくというのは、体とダイレクトに繋がっているからこそ得られる感覚なのでしょうか。写真でも同じようなことを感じる瞬間はありますか?
壹岐:写真は、カメラを持って絵を作るのでダンスのようにはいきません。ダンスは自分が感じることだけに集中できる。ダンスで得られる感覚をビジュアル化したい。そんな想いで「DANCE」という作品を撮り始めました。

仕事としての写真を離れ、自分自身に向き合ったNY生活
Sayaka:ブランド10周年のコラボレーションでは、多重露光による壹岐さんの作品「DANCE」を生地にプリントし、カプセルコレクションにさせて頂きました。この作品を撮り始めたきっかけはなんだったのでしょう?
壱岐さん:夫の意向もあり、2015年の秋から2019年まで拠点をNYに移したのですが、ちょうど気持ち的にも息継ぎをしたいと思っていた時期でした。20代後半はカメラマンの仕事が忙しくて、同時に踊る機会もたくさんあったので、平日は忙しく仕事をして週末は踊ってまた仕事をして...という生活を続けていたので、いったん全てをストップして自分だけの時間を持ちたいと思っていたんです。
NYに到着し、空港出て電車に乗ったら、乗っている全員人種が違うことに感動しました。世界各地では争いが起こっているけれど、NYではいろんな国の人がこうやって同じ車両に乗っている、こんな世界があるんだって。同時に私ってどんな人なんだろう、どういう人間なんだろうと考えさせられました。ここで生きていくためには自分のやりたいことをやって、自分がどんな人間なのか理解したい。そんな気持ちをNYという環境が後押ししてくれた気がします、Sayakaさんを含め、NYで知り合った人たちは自分を生きている人たちばかり。私もそういうふうに生きたいと強く思いました。それが自分の表現を深めていきたいと思ったきっかけになっていると思います。
Sayaka:NYって人のエネルギーがすごい。その熱に触れて自分が何をやりたいか考えさせられたという壹岐さんのお話には、私も共感するところがあります。

目に見えない感覚、自然との一体感を撮り重ねることで表現
壱岐:自分自身を表現したいと思った時、ダンスで得られる自然との一体感、自然と共に踊っている感覚を写真で表現できたら面白いなと思い、踊ったり動いたりしながら撮った写真を重ねていく多重露光という手法に辿り着きました。
Sayaka:撮影している時は仕上がりをある程度予想しているんですか?それとも感覚的に、体が動くままにシャッターを押しているんでしょうか?
壹岐:両方ありますね。経験を重ねるうちに、最近はこうなるんじゃないかという予想に近しいことができるようになってきました。一方で狙っても狙ったように撮れない部分もありますし、どんなに撮り続けても見たことのない絵がでてくる。この速さでこの回数重ねるとこうなるという可能性が何万通りもあるから飽きることがないし、この先にもっと何かあるんじゃないかという感覚で撮り続けいます。
Sayaka:初めて「DANCE」のダンスの作品を撮った時、自分の中で「これだ」というものをクリックしたような感覚はありましたか?
壹岐:目に見えないものや、ダンスで感じた感覚をどうやったら表現できるんだろう。とずっと思ってきたのですが、「あっこれだ」という感覚がありました。自分の動きを入れることができるし、パッと見た時に「これはなんだろう?どう撮ったんだろう?」という想像力を掻き立てることができる。曖昧さや揺れ動く感覚など、自分が表現したいものに近い手法を見つけた気がします。今この瞬間に目でみているものの過去にはたくさんの積み重ねがあるし、自然も長い積み重ねの上に出来上がっている。撮り重ねる手法は、それに繋がるものがあると思っています。
Sayaka:これからも「DANCE」の作品を続けて行きたいですか?今後の展望を教えてください。
壹岐:2019年に帰国し出産してからは、子育てや仕事が忙しかったり、コロナ禍の影響もあったりして海外に行けない状況が続いていましたが、今はまた海外で作品を撮りたいという気持ちが強いです。そんな中、Sayakaさんとのコラボレーションが、私の作品に新しい命を吹き込んでくれた気がしてとても嬉しかったです。「DANCE」という作品を通してたくさんのギフトをいただいた気がしますし、自分を表現する方法として、これからもずっと続けていきたいと思っています。


写真家
壹岐 倫子
愛知県名古屋市生まれ。地元名古屋でカメラマンとして活躍した後、2015年にニューヨークに渡り、多重露光による作品「Dance」を発表。2019年にはベネチア国際アルテラグーナ賞ファイナリストに選出、ニューヨーク「The Blanc Art Show2019」に出品するなど国際的に注目を集める。ダンスや旋回などの身体的表現を通じて感じた普遍的な欲求や自然観、女性性などをテーマに、写真での表現に取り組んでいる。
Instagram:@ikico / HP:tomokoiki.com